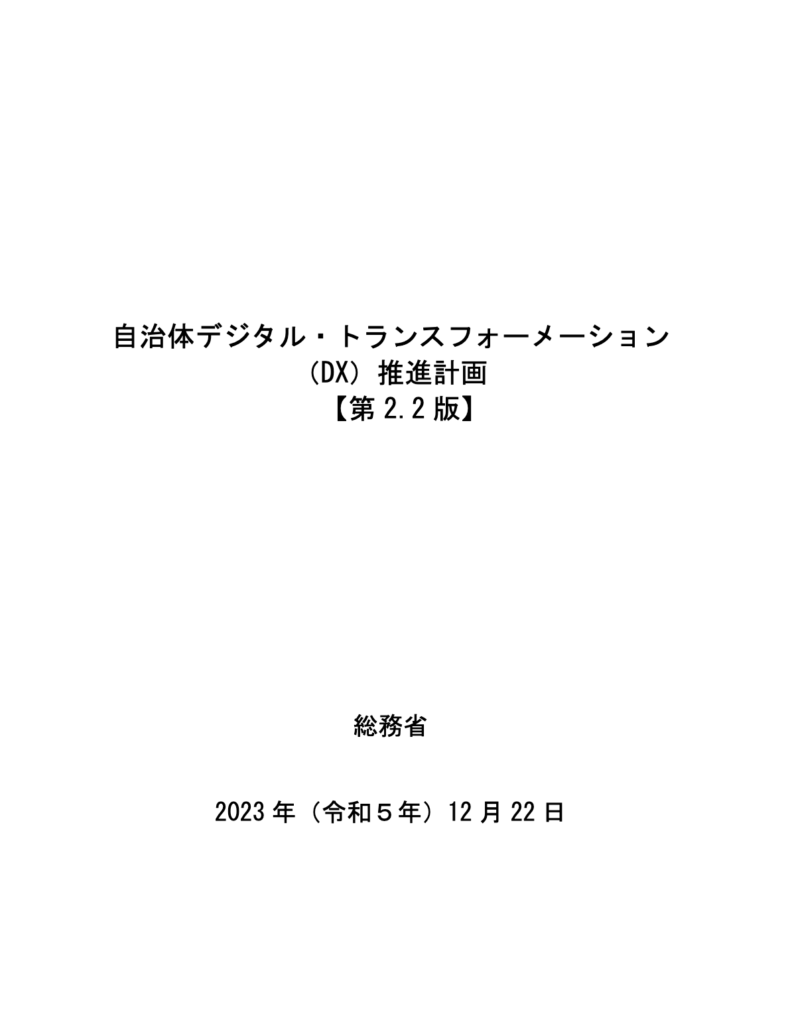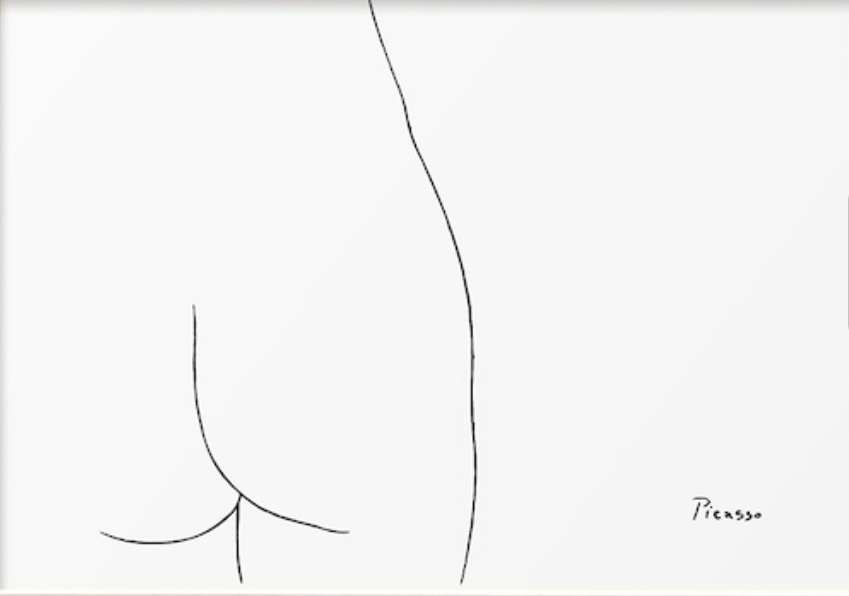まちづくりの一環で、自治会(いわゆる、公民館。地域コミュニティ)と、福祉団体のそれぞれで、ワークショップを実施した。
テーマは「現状の課題と、まちづくりに期待すること」。大学生にも協力してもらって、みなさんと一緒にグループを作って、ディスカッションしてもらった。
結果、非常に良いディスカッションをすることができた。なぜなら、日頃つながりのない人たちをつないで、それぞれの立場を理解してもらうことで、お互いのメリットになったと実感できたからだ。
作戦は成功。世代間の地域交流は、みんなの役に立つ。
もともとの考えとしては、
大学生にとっては、社会のプレーヤとしての参画、社会貢献への第一歩、世代間ギャップからの学びがあるだろうからWinになるだろうと思っていたし、
自治会の会員(主に高齢者)と福祉団体のスタッフ(いわゆる障がい者の方々)にとっても、大学生とのつながりがないだろうから良い刺激になってWinとなるだろうと、
思っていた。
幸いにも、その考えはあたっていたようで、ディスカッションは盛り上がっていたし、実施後に、継続実施を希望といった反響もいただいた。大学生も、笑顔で積極的に発言してくれていた。
自治会の抱える課題は、会員を増やすこと。これが最も意見が多かった。会員を増やしたいけど、自分たち高齢者からは、若者に声掛けしづらいとか、年々減少する会員数への対策が打てないでいる現状があった。
対して学生からは、InstagramなどのSNSを活用することや、自治体ホームページへの掲載による呼びかけなどについてのアイデアが出ていた。
福祉団体とのディスカッションでは、障がい者といってもそれぞれの特徴があって、コミュニケーションを取る場合は、まずは自分がどういう障がいを持っているかを伝えることが大事など、正直、思っても見なかった意見をいただいて青天の霹靂だった。
ゆっくり話してほしいとか、絵を使ってほしいとか、漢字にはルビをふってほしいとか、コミュニケーションをするための条件・前提を伝えることが、まず重要で、だから、自治体職員が交代するのは結構なストレスになるんだ、ということも知ることができた。
すなわち、いかに僕自分が「目を向けてなかったか」もしくは「分かっている気になっていたか」を痛感させられたということであって、良い意味で大きなショックを受けた。
大学生も「知らなかったことだらけだった」と、決して後ろ向きじゃなく、前向きな反応をしてくれていた。
現場を知ること、現場で活動することの大切さを改めて実感したし、こういった活動を継続することが、本当の意味のまちづくりにつながるんだな、とも痛感できた。どうにかして、継続したい。
継続性と、ビジネスと、テクノロジと。これからの時代でも取り組み続けるためのアイデア。
実施後、興奮冷めやらぬ状態で色々と考えていた。一番のトピックは「なぜ、人は他人を知ろうとしないのか」ということだった。結論から言うと、「社会的なカテゴリって不要だな」ということ。
正直、実施する前は、「高齢の方や、障がいをお持ちの方と、普通に話せるだろうか?」と、一抹の不安を抱いていたのだが、やってみたら全くの杞憂だった。話してみたら、そんな不安など完璧に忘れていて、普通に話していた自分がいた。恥ずかしさを覚えるくらいの杞憂だった。
そういった景観と、ワークショップをやった結果から、「男性・女性」とか、「若者・高齢者」とか、「健常者・障がい者」とか、カテゴリの大事さを分かっている一方で、カテゴライズすることで、同じ人間でも価値基準や思考に影響が出て、あたかも違う人種のようになるのではないか? カテゴリの影響は大きいのではないか?と考えを巡らすようになってきた。
とどのつまり、「敵と味方」を作ってしまうので、めんどうなのだ。
仮に、カテゴリによって「自分とそれ以外」のようなボーダーを引いてしまっていて、引いてしまったせいで余計な不安や考えを抱くのだとしたら、行動することを躊躇する理由になっているとしたら、本当にもったいない。逆に、なければもっと行動しやすかったり、日常生活でもお互いにコミュニケーションしやすかったりするのではないだろうか。
人間が本能的・原始的にカテゴライズしたりボーダーを引いてしまうとしたら、理性的に教育という手段で乗り越える仕組みを作りたい。継続してみたい。そのためにも、ビジネスにしたい。
まちづくりは、継続することが大事だけれど、継続する体制を作って維持することは難しいのかもしれない。なぜなら、ビジネスになりづらいから。では、なぜビジネスと言っているかというと、資本主義社会においては、ビジネスが社会やステークホルダを幸せにする手段と僕は信じているから。
具体的に言うと、社会貢献などの「やるべきこと、一般的に良いこと」があったとしても、「その人の日常生活を支えてくれるものではない=お給料がもらえるわけじゃない」から、実施体制を責任を持って作って、継続運営する拘束力が弱い、ということだ。
よって、まちづくりもビジネスにすべきだと思っているし、一方で、規模の大きなビジネスにも、スケールするビジネスにもなりづらいだろうという逆の考えもあって、ジレンマに近い感情を抱く。
オープン、ボーダレス、各自のアクティビティについての社会的な信用の確立。そのためのNFT。
テクノロジが非常に進化していて、そのスピードも非常に速いし速くなり続けるだろうこれからの時代では、ビジネスのあり方を含めて、人間はもっとオープンに、ボーダレスになっていくのだろうと考えている。
そのためにも、NFTを活用したい。NFTは、個人のアクティビティを一意に証明できるテクノロジのはずだ。地域貢献活動に対して、その地域の自治体がお墨付きとして発行するNFTがあれば、各自は活動した結果を社会的信用をもって、大概的にアピールできるのではないか。就職活動とかにも活用できる気がする。
まちづくりは、ロングタームなビジネスとして伴奏型コンサルをしつつ、関係する人にも給与とNFTという形で還元する。場合によっては、各自の対外アピールもサポートすると良いかもしれない。ビジネス化できるのではないか?
継続して考えつつ走ってみよう。たのしいし、ワクワクする。行ける気がする。