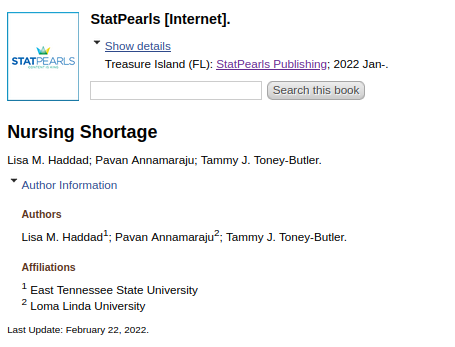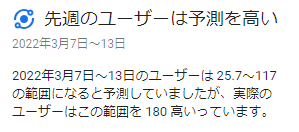僕は人生で外せないものが3つある。①Art、②Technology、そして③English。それぞれのカテゴリで2019年を振り返ってみる。
が、今回は④その他ということで、全体的に振り返ってみる。
【2月】台湾へ
仕事のつながりで台湾に友達ができた。業務で行きたかったが、会社が許可をくれないので、プライベートで台湾へ。
友達にリアルで会えたこと、多くを語り合えたこと、仕事の現場に行けたこと、現場は台湾の小学校で、視察がてらサプライズで小学校の授業に外国語講師みたいな感じで参加できたこと、夜市を楽しめたこと、そして朝市を超楽しめたことと、良い思い出ばかりだ。
現地視察だけのつもりだったのが、構内を案内してくれるし、その上、授業にゲスト出演させてもらえたのがとても良い経験になった。ちなみに、外国語の授業で、日本語の紹介部分で登場。
「おじさん」と「おじいさん」の発音が難しいらしく、専門の先生も聞き分けることができなかったという事実を体験できたのがとても良かった。みんなの前でRepeat after meということで、「おじさん」と「おじいさん」と連呼。
普段英語を学習している時は生徒でしかなかったので、逆の立場になれたことが新鮮で楽しかった。
台湾と言えば夜市。高尾に行ったのだが、高尾でも有名なトップ2つの夜市へ。友達に案内してもらう。すごく安心。
屋台でアヒルの足も食べる。見た目はグロテスク。だけど、味は結構おいしい。
やってやれ、ということで、何でも食べた。お腹壊さなくてよかった。台湾は安心。
もともと早起きで、台湾でも早起き。早朝、まだ街が眠っている時間帯を一人で散歩がてら散策。すると、意図してなかったが朝市に出くわした。
これがまた最高で、どう最高かと言うと、現地の方の生活をとても感じることができるので最高だった。
エネルギッシュ。とにかく、何か、パワーを感じた。朝というだけでエネルギッシュなのに、高尾の人たちの雰囲気があいまって、かつ、ほぼ初めての海外というエキサイトさも相まって、最高の経験だった。
世界の朝市を巡りたいと思ってきっかけとなった。
まだまだ多くを語りたいけど、長くなりすぎるので割愛。
【6月】人間ドックで100点満点ゲット
胃が痛かった。空腹だろうが、平時だろうが、満腹だろうが、とにかく常に痛い。とうとう胃がんでも患ったか、と覚悟して人間ドックを受信。
結果、お医者さんから「100点満点です。すごいです。こういう人めったにいません」と言われる。
「あの、、、胃が常に痛いんですが」と聞いたところ、「胃もすごくキレイです。ピロリ菌の心配もありません」とのこと。
うん、安心して爆進するぞ。
【6月】JASK Youthのイベント実施
以下を読んでいただきたい。
2019年の振り返り③(English編) | hiro-lab
【7月】トークイベントLabホワイエを開催
「軽めのイベントやってみよう。単純に楽しむだけのやつ」と思ってやってみたのが、このトークイベント。僕の知り合いで、思慮深い方がいらっしゃったので、その方の生い立ちや考えていることを紹介する、という内容でやってみた。
結果、こじんまりとしているが15人程集まって、ワイワイ楽しむことができた。
イベントとなると大きなものをしっかりやらないととか、継続と発展が必要だ、とかをかなり意識してしまっていたが(もちろん今でも大事だと思っているし意識しているが)、この時は、そういうのは置いといてまずやってみよう、とやることメインで実施。
結果、小規模ながらも内容が濃いイベントとなったし、小さいイベントの運営を肌感覚で覚えることもできたので、とても良い経験となった。
<<写真入れる>>
【8月】サンアントニオへ
JASKの活動で、熊本県の高校生を、熊本市の姉妹都市であるアメリカ>テキサス州>サンアントニオへ派遣。僕はその引率を務めた。
これがまた大変で、学生は高校1年と2年だったんだけど、よくよく考えると中学生に近い子たちばかりで、引率がとても大変だった。
中でもコミュニケーションの取り方と、自主性のバランスが難しく、正直、渡米期間中、ずっと悩みっぱなしだった。
結果、ホストファミリーとも良い関係を築いてもらったし、別れの際は涙も流れていたしで、成功だった。
本当に悩みっぱなしだったし、トラブルも多い旅だったけど、良い経験をさせてもらった。
それに僕自信、ホストファミリーにとても良くしてもらい、非常に良いご縁をいただいた。人生の財産の一つとなった。
(学生とのコミュニケーションに関する経験は、別投稿しようと思っている。JASK Youthも含めて)
【9月】コンサルティング開始
英語関係のコンサルティングを開始。依頼者からは信頼を得ていて、自由にやりたいことをさせていただいている。
自分が考えたことを、スピーディに了承いただいて、実践できるって、本当に幸せ。
もちろん成功が必須というプレッシャーはある。けれど、チャレンジさせてもらっている分、幸せの方が勝っている。ガンガン進めよう。このことに関しては特に、やる気の塊になっている。
ちなみに、2019年12月現在、継続中だ。
【10月】龍田プレイパークイベントの撮影
以下を読んでいただきたい。
2019年の振り返り①(Art編) | hiro-lab
【10月】コミュニティナースイベントの撮影
以下を読んでいただきたい。
2019年の振り返り①(Art編) | hiro-lab
【11月】Global Challengeイベントに参加
福岡市が主催のGlobal Challenge Startup に参加させてもらっている。海外研修コースと国内研修コースがあって、僕は海外研修コースで応募したのだが残念ながら落選し、国内研修コースを受講していた。
が、運良く海外研修コースの枠が空いて、名指しでどうだ?と言われたので、飛びついた。ものすごくラッキーだ。
それに、スタートアップという同じ志をもつ方々と出会えたことも、人生の財産となった。独特の熱量がある。そして、ガツガツしている。ギラギラしている。その雰囲気が心地よい。
ビジネスの話を本気で話せる人って、あまりいなかった。けど、Global Challengeのメンバーは普通に話せる。だから、とても楽。嬉しい。
ということで、2020年も引き続きディスカッションしまくり、話しまくり、行動しまくりで行く予定。
【11月】英語deプログラミングイベント実施
英語関係コンサルティングの一環で、プログラミング授業を英語で実施するイベントを開催。これは熊本だけでなく、全国的にも珍しい、先進的な取り組み。
イベントの企画、構成、実行と、始めから終わりまでを担当。もちろん、レクチャーする講師のトレーニングも、当日のサポートも。
これは確実にニーズが出てくるものだし、いち早く実現することで先行者利益も多く期待できるので、スピーディに実現できたことは評価に値すると思っている。
今後も、第2弾、第3弾と実施の予定。どうなるかワクワクする。
<<写真を入れる>>
【11月】防災ICTクラブに参加
総務省の事業の一環で、熊本県の崇城大学が採択された「防災ICTクラブ」にメンターとして参加。11月から12月まで、ほぼ全部の土日を費やした。
「地域のICT人材を育てて地域復興の一助とする」ことを目的としたこの催しは、熊本県でイノベーションを起こせる人材をというテーマで、参加する小中高校生をスーパーキッズにする!と豪語して(実際に参加者に熱く言っている)取り組みを進めた。
具体的には、ラズパイを使った被災時の避難経路表示や、Googleサービスの使い方、Twitterデマ情報の見分け方、ドローン演習と、結構幅広に実施していて、多くの小中高校生に刺激を与えた良い取り組みだった。
SCBラボ「みんなの防災ICTクラブ」がスタート | 崇城大学
みんなの防災ICTクラブニュース④ | SCB LAB for Social Community Brand
僕は、講師、サポーター、フォトグラファー、そして実務ぐりぐり回すという役割を実施。成果発表会ではPA周りを担当。全力で取り組んだ。
結果、学生も笑顔で楽しんでくれていて、口々に良い経験をしたと言ってくれたので、成功したと思っている。僕も、良い経験をさせてもらった。
【12月】人生初のニューヨークへ
以下を読んでいただきたい。
My First New York City in 2019.|はたただひろ|note
2019年の振り返り①(Art編) | hiro-lab
【12月】TONAKAI DONATION PARTYに参加
以下を読んでいただきたい。
2019年の振り返り①(Art編) | hiro-lab
振り返ってみての感想
2019年は結構アクティブに動いた年だったと思う。特に、海外に3回行ったのは大きい。イベントも多数実施したり、多くのステキな出会いもあったりご縁もいただいた。
悩んでいたことも道が見えてきた。
自分がいかに愛を欲しているかも分かったし、他の面も自分を見つめ直し深堀りすることができた。
人間として大きく成長できた。
2020年も、大きく成長する。